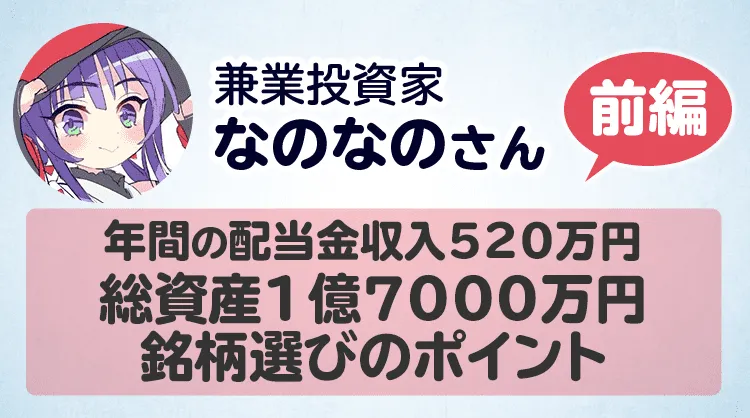産業育成は政府の仕事か? むしろ発展を妨げた戦後の歴史(木村貴の経済の法則!) - |QUICK Money World -

【QUICK 解説委員長 木村貴】政府は新しい産業の育成に熱心だ。日本経済新聞によると、6月下旬にまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)の原案で、次世代半導体の量産に向けて、法整備の方針を盛り込んだ。 政府が …
個人投資の未来を共創するQUICKの金融情報プラットフォーム
記事公開日 2024/6/7 12:00 最終更新日 2024/6/7 16:42 二輪車自動車木村貴家電木村貴の経済の法則!
 クリップする 【QUICK 解説委員長 木村貴】政府は新しい産業の育成に熱心だ。日本経済新聞によると、6月下旬にまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)の原案で、次世代半導体の量産に向けて、法整備の方針を盛り込んだ。
クリップする 【QUICK 解説委員長 木村貴】政府は新しい産業の育成に熱心だ。日本経済新聞によると、6月下旬にまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)の原案で、次世代半導体の量産に向けて、法整備の方針を盛り込んだ。
政府が次に国を牽引する産業部門を選び、その産業を補助金などの優遇措置によって保護し育成する政策を「産業政策」と呼ぶ。現在は経済産業省がその主な担い手で、赤字続きで批判を浴びた「クールジャパン戦略」などを主導してきた。
政府が将来の成長産業を選び、育成するという発想は、自由な市場経済にはそぐわない。それでも産業政策が盛んな一つの理由は、「戦後、経産省の前身である通商産業省の産業政策が有効に機能し、奇跡といわれた高度経済成長に貢献した」という通念が根強いことにある。
しかし実際には、戦後の産業政策は有効に機能しなかったばかりでなく、むしろ産業の発展を妨げた。高度成長期に日本の基幹産業へと成長し、世界市場までも制するに至った、自動車産業を例に検証してみよう。
自動車産業が急成長した理由
今では想像できないかもしれないが、1950年代前半まで、自動車は日本では存立不可能な産業だとみなされていた。60年代に入ってモータリゼーション(車の大衆化)が急速に進展する時代となっても、日本車、とくに乗用車は国際競争力を欠く産業だとされた。たとえば1950年4月の日経新聞で、当時の一万田尚登日銀総裁は「輸出を伸ばすとはいっても国際分業のたてまえに沿うべきで、たとえば日本で自動車工業を育成しようと努力することは意味をなさぬ」と発言していた。
そうした杞憂をよそに、日本の自動車産業は急成長を遂げた。その要因とされたのは、通産省による国産自動車保護・育成策だ。外国会社による自動車輸出、資本輸出に厳しい制限措置をとる一方、国産メーカーに対して外国メーカーとの技術提携の促進、政府系金融機関の低利資金供与などを実施した。
経済学者の宇田川勝氏は、自動車産業の戦後再出発時において通産省の果たした役割は大きかったとしながらも、その保護・助成策だけで日本の自動車産業の発展が可能となったと考えることはできないと述べる。実際には「自動車業界は通産省の産業政策あるいは行政指導に唯々諾々と従ったわけでは決してなく、それらをめぐって両者が鋭く対立する場面も少なくはなかった」(『日本の自動車産業経営史』)。
たとえば、通産省は1955年、「国民車育成要綱案」を発表した。最高時速100キロ以上、定員4人、エンジン排気量350~500cc、燃費1リットルあたり30キロメートル以上、販売価格25万円以下——という条件を満たす乗用車を各メーカーに試作させ、最優秀の1車種を国民車に選定し、財政資金を投入して育成を図るとの構想だった。しかし自動車業界は、機会均等と自由競争の原則に反するとして賛成せず、結局、国民車構想は日の目を見ずに終わった。
1960年代に入ると、通産省は「グループ化構想」を打ち出した。貿易・資本の自由化に対処するため、自動車業界を量産車、特殊車、ミニカー生産の3グループに集約することを狙ったものだ。各メーカーの合同策も試みた。この構想も業界の抵抗で実現できず、合同策もさしたる成果を上げることができなかった。
通産省による国民車構想や業界再編策が成功しなかった理由の一つは、トラック・バス、二輪車などから乗用車分野への参入を目指す多数の後発メーカーが存在したことにある。国民車構想に対しては、後発メーカーは反対の急先鋒に立って業界として頓挫に追い込む一方、したたかにも国民車の諸条件をクリアする軽・小型車の試作・生産に挑んだ。
 (トヨタ博物館、wikipedia.org)
(トヨタ博物館、wikipedia.org)
その一つが富士重工業(現SUBARU)の「スバル360」だ。日本での自家用車の普及は、政府の方針にとらわれることなく開発されたスバル360の功績であり、国民車構想の影響はほとんどないとする見方もある。
後発メーカーはグループ化構想に対しては、実施に移される前に乗用車メーカーとしての地位を確保しようと、先を争って乗用車に参入した。通産省の策は裏目に出て、業界再編とは逆の方向に作用し、多くの企業の乗用車分野への駆け込み参入を促す皮肉な結果をもたらした。
こうして日本の自動車産業には異質の技術力・経営力を備えた企業が次々に登場した。その結果、乗用車メーカーだけで10社(2024年現在は日野自動車、いすゞ自動車が撤退し8社)がしのぎを削るという、他の自動車主要生産国には類を見ない、激しい競争環境が実現することになる。これが世界市場を席巻する実力を育んだ。自動車メーカーが通産省におとなしく従うだけだったら、その後の隆盛はなかっただろう。
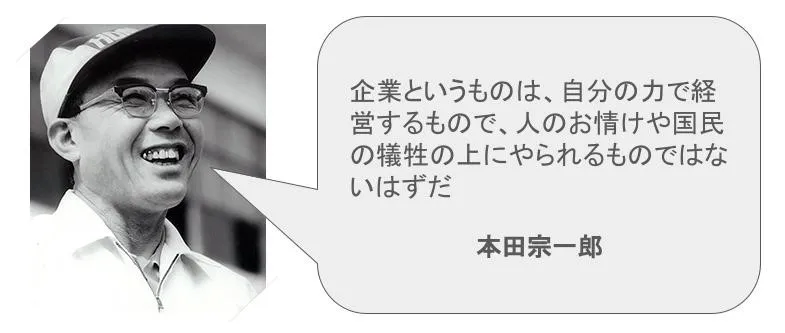 global.honda
global.honda
後発メーカーの一つ、ホンダの創業者・本田宗一郎氏は四輪車に参入する前、当時の国産車メーカーを念頭にこんな言葉を残している。「なかには政府の手厚い保護を頼りに生きている業界があるから、いつまで経ってもよちよち歩きから成長できない。企業というものは、自分の力で経営するもので、人のお情けや国民の犠牲の上にやられるものではないはずだ」(『ざっくばらん』)
オートバイ産業の激しい競争
自動車だけではない。戦後の早い時期に、政府の政策の関与を受けることなく、世界に冠たる産業としての地位を築いた産業はいくつもある。カメラ、双眼鏡、ミシン、オートバイ、ピアノなどがその例だ。また近年、日本人の生活を大きく変えたビジネスの代表として、宅配便、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ファーストフード、ファミリーレストラン、人材派遣などがある。このうち政府の政策が発展の障害となったものこそあれ、産業の発展を促したものはないと、経済学者の三輪芳朗、J・マーク・ラムザイヤー両氏は共著で指摘する(『産業政策論の誤解』)。
たとえば、オートバイ産業だ。戦後、オートバイがブームとなったのは1952〜53年ごろだった。富塚清『日本のオートバイの歴史』によると、それ以前には、さまざまな障害があって、八方ふさがりの状況だった。障害とは①めぼしい工場は連合軍に押さえられている②材料不足で配給制③燃料も統制で入手困難④燃料の質が不良⑤ユーザー側が預金封鎖や新円切り替えなどで現金に乏しい——などだ。
その後、ガソリン事情の好転などを反映して、企業数と生産台数が激増した。生産台数が著しく少ないメーカーを除いても、戦後スタートした戦後派メーカーが100社以上あった。「陸王」「みづほ」「ミヤタ」「メグロ」などの戦前からのメーカーがこれに加わって激しく競争した。企業の淘汰が急速に進み、戦前からの伝統ある企業はことごとく敗退。戦前派のうち最後に残ったメグロも1964年に事業をカワサキに移譲して撤退した。この時点で残った6社からさらにブリヂストンが転業、富士重工が二輪車業を停止し、残ったホンダ、スズキ、ヤマハ、カワサキの4社が今日まで競争を続けている。
この業界再編に、政策は関与しなかった。新製品の開発、製品の改良や品質向上、価格低下などに政策が関与し、貢献したという話もない。
電器製品にも政府は関与せず
家庭に急速に普及した電器製品も同様だ。かつて洗濯は「洗多苦」と書くといわれたほどに、主婦が洗濯板とたらいを使って、赤ちゃんのいる家庭ならおむつなどを毎日3時間も4時間も洗い続ける、長時間を要する水仕事だった。洗濯機の登場でその負担が軽減された。冷蔵庫も、生鮮品を家庭でストックできる可能性を開き、買い物の回数や買い方を変える契機になった。テレビとともに「三種の神器」と呼ばれたこれら電器製品が登場した1949〜59年に、1日の家事時間は10時間16分から9時間2分に短縮された。さらに70年代には7時間台に減少した(武田晴人『高度成長』)。
 wikipedia.org
wikipedia.org
女性の負担を軽くし、日本人の暮らしを豊かにした、これら電器製品の開発、普及にも政府は関わっていない。政府の産業政策が高度成長をもたらしたという主張は、根拠に乏しい神話でしかない。
産業育成は政府の仕事ではない。民間の自由な選択に任せたほうが経済は繁栄する。これが高度成長の真実であり、日本経済の未来にとっての教訓といえる。政府がある産業を熱心に支援しようとしたら、株式は売りのタイミングかもしれない。
今では想像できないかもしれないが、1950年代前半まで、自動車は日本では存立不可能な産業だとみなされていた。60年代に入ってモータリゼーション(車の大衆化)が急速に進展する時代となっても、日本車、とくに乗用車は国際競争力を欠く産業だとされた。たとえば1950年4月の日経新聞で、当時の一万田尚登日銀総裁は「輸出を伸ばすとはいっても国際分業のたてまえに沿うべきで、たとえば日本で自動車工業を育成しようと努力することは意味をなさぬ」と発言していた。
そうした杞憂をよそに、日本の自動車産業は急成長を遂げた。その要因とされたのは、通産省による国産自動車保護・育成策だ。外国会社による自動車輸出、資本輸出に厳しい制限措置をとる一方、国産メーカーに対して外国メーカーとの技術提携の促進、政府系金融機関の低利資金供与などを実施した。
経済学者の宇田川勝氏は、自動車産業の戦後再出発時において通産省の果たした役割は大きかったとしながらも、その保護・助成策だけで日本の自動車産業の発展が可能となったと考えることはできないと述べる。実際には「自動車業界は通産省の産業政策あるいは行政指導に唯々諾々と従ったわけでは決してなく、それらをめぐって両者が鋭く対立する場面も少なくはなかった」(『日本の自動車産業経営史』)。
たとえば、通産省は1955年、「国民車育成要綱案」を発表した。最高時速100キロ以上、定員4人、エンジン排気量350~500cc、燃費1リットルあたり30キロメートル以上、販売価格25万円以下——という条件を満たす乗用車を各メーカーに試作させ、最優秀の1車種を国民車に選定し、財政資金を投入して育成を図るとの構想だった。しかし自動車業界は、機会均等と自由競争の原則に反するとして賛成せず、結局、国民車構想は日の目を見ずに終わった。
1960年代に入ると、通産省は「グループ化構想」を打ち出した。貿易・資本の自由化に対処するため、自動車業界を量産車、特殊車、ミニカー生産の3グループに集約することを狙ったものだ。各メーカーの合同策も試みた。この構想も業界の抵抗で実現できず、合同策もさしたる成果を上げることができなかった。
通産省による国民車構想や業界再編策が成功しなかった理由の一つは、トラック・バス、二輪車などから乗用車分野への参入を目指す多数の後発メーカーが存在したことにある。国民車構想に対しては、後発メーカーは反対の急先鋒に立って業界として頓挫に追い込む一方、したたかにも国民車の諸条件をクリアする軽・小型車の試作・生産に挑んだ。
 (トヨタ博物館、wikipedia.org)
(トヨタ博物館、wikipedia.org)
その一つが富士重工業(現SUBARU)の「スバル360」だ。日本での自家用車の普及は、政府の方針にとらわれることなく開発されたスバル360の功績であり、国民車構想の影響はほとんどないとする見方もある。
後発メーカーはグループ化構想に対しては、実施に移される前に乗用車メーカーとしての地位を確保しようと、先を争って乗用車に参入した。通産省の策は裏目に出て、業界再編とは逆の方向に作用し、多くの企業の乗用車分野への駆け込み参入を促す皮肉な結果をもたらした。
こうして日本の自動車産業には異質の技術力・経営力を備えた企業が次々に登場した。その結果、乗用車メーカーだけで10社(2024年現在は日野自動車、いすゞ自動車が撤退し8社)がしのぎを削るという、他の自動車主要生産国には類を見ない、激しい競争環境が実現することになる。これが世界市場を席巻する実力を育んだ。自動車メーカーが通産省におとなしく従うだけだったら、その後の隆盛はなかっただろう。
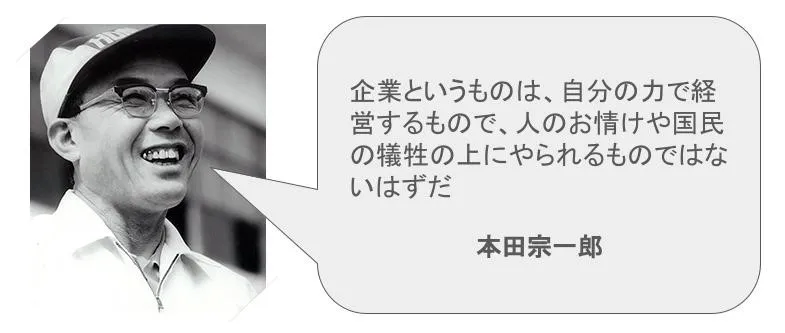 global.honda
global.honda
後発メーカーの一つ、ホンダの創業者・本田宗一郎氏は四輪車に参入する前、当時の国産車メーカーを念頭にこんな言葉を残している。「なかには政府の手厚い保護を頼りに生きている業界があるから、いつまで経ってもよちよち歩きから成長できない。企業というものは、自分の力で経営するもので、人のお情けや国民の犠牲の上にやられるものではないはずだ」(『ざっくばらん』)
オートバイ産業の激しい競争
自動車だけではない。戦後の早い時期に、政府の政策の関与を受けることなく、世界に冠たる産業としての地位を築いた産業はいくつもある。カメラ、双眼鏡、ミシン、オートバイ、ピアノなどがその例だ。また近年、日本人の生活を大きく変えたビジネスの代表として、宅配便、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ファーストフード、ファミリーレストラン、人材派遣などがある。このうち政府の政策が発展の障害となったものこそあれ、産業の発展を促したものはないと、経済学者の三輪芳朗、J・マーク・ラムザイヤー両氏は共著で指摘する(『産業政策論の誤解』)。
たとえば、オートバイ産業だ。戦後、オートバイがブームとなったのは1952〜53年ごろだった。富塚清『日本のオートバイの歴史』によると、それ以前には、さまざまな障害があって、八方ふさがりの状況だった。障害とは①めぼしい工場は連合軍に押さえられている②材料不足で配給制③燃料も統制で入手困難④燃料の質が不良⑤ユーザー側が預金封鎖や新円切り替えなどで現金に乏しい——などだ。
その後、ガソリン事情の好転などを反映して、企業数と生産台数が激増した。生産台数が著しく少ないメーカーを除いても、戦後スタートした戦後派メーカーが100社以上あった。「陸王」「みづほ」「ミヤタ」「メグロ」などの戦前からのメーカーがこれに加わって激しく競争した。企業の淘汰が急速に進み、戦前からの伝統ある企業はことごとく敗退。戦前派のうち最後に残ったメグロも1964年に事業をカワサキに移譲して撤退した。この時点で残った6社からさらにブリヂストンが転業、富士重工が二輪車業を停止し、残ったホンダ、スズキ、ヤマハ、カワサキの4社が今日まで競争を続けている。
この業界再編に、政策は関与しなかった。新製品の開発、製品の改良や品質向上、価格低下などに政策が関与し、貢献したという話もない。
電器製品にも政府は関与せず
家庭に急速に普及した電器製品も同様だ。かつて洗濯は「洗多苦」と書くといわれたほどに、主婦が洗濯板とたらいを使って、赤ちゃんのいる家庭ならおむつなどを毎日3時間も4時間も洗い続ける、長時間を要する水仕事だった。洗濯機の登場でその負担が軽減された。冷蔵庫も、生鮮品を家庭でストックできる可能性を開き、買い物の回数や買い方を変える契機になった。テレビとともに「三種の神器」と呼ばれたこれら電器製品が登場した1949〜59年に、1日の家事時間は10時間16分から9時間2分に短縮された。さらに70年代には7時間台に減少した(武田晴人『高度成長』)。
 wikipedia.org
wikipedia.org
女性の負担を軽くし、日本人の暮らしを豊かにした、これら電器製品の開発、普及にも政府は関わっていない。政府の産業政策が高度成長をもたらしたという主張は、根拠に乏しい神話でしかない。
産業育成は政府の仕事ではない。民間の自由な選択に任せたほうが経済は繁栄する。これが高度成長の真実であり、日本経済の未来にとっての教訓といえる。政府がある産業を熱心に支援しようとしたら、株式は売りのタイミングかもしれない。
 著者名木村貴(QUICK解説委員長)
著者名木村貴(QUICK解説委員長)
日本経済新聞社で記者として主に証券・金融市場を取材した。日経QUICKニュース(NQN)、スイスのチューリヒ支局長、日経会社情報編集長、スタートアップイベント事務局などを経て、QUICK入社。2024年1月から現職。業務のかたわら、投資のプロに注目される「オーストリア学派経済学」を学ぶ。著書に「反資本主義が日本を滅ぼす」「教養としての近代経済史」ほか。

 クリップする 【QUICK解説委員長 木村貴】「インフレ」とは学校で誰もが教わり、メディアでもよく目にする経済の基本用語だ。日銀が2%の「インフレ目標」を掲げるように、インフレとは「全体的な物価水準が持続的に上昇する状態」とされる。要 … 2024/5/31 13:32 【QUICK解説委員長 木村貴】前々回と前回で説明したように、お金は政府によって計画・考案されたものではなく、個人の行動から自然に生まれたものだ。また、長い歴史を経て、人々は優れたお金として貴金属である金と銀を選び取った … 2024/5/24 16:53 【QUICK解説委員長 木村貴】国債は株式などと同様に市場で売買されており、価格は変動するため、券面に記された利率が同じでも、購入した時の価格によって満期までに得られる利回りは違ってくる。満期までに受け取る利息が同じなら … 為替・金利 2024/5/23 14:01 【QUICK解説委員長 木村貴】お金は前回説明したように、商品から生まれる。だからお金として使う以外に、商品として使うことができる。まもなく新札が登場する日本円をはじめ、現代のお金はお金以外に使い道がない。これはお金本来 … 2024/5/17 13:52 【QUICK解説委員長 木村貴】日銀の政策変更や急激な円安など、「お金」にまつわるニュースが相次いでいる。そもそもお金とは何か、その基本のキについてあらためて考えてみよう。 あなたが絶海の孤島に流れ着いたとしよう。あたり … 2024/5/10 14:46 【NQNロンドン=蔭山道子】欧州株式市場で自動車株の上値が重い。電気自動車(EV)を中心とした需要減や中国での競争激化などで2024年1~3月期は各社、販売が苦戦した。新車種の投入などをきっかけとした先行きの収益回復に期 … NQNセレクト 2024/5/8 12:45
クリップする 【QUICK解説委員長 木村貴】「インフレ」とは学校で誰もが教わり、メディアでもよく目にする経済の基本用語だ。日銀が2%の「インフレ目標」を掲げるように、インフレとは「全体的な物価水準が持続的に上昇する状態」とされる。要 … 2024/5/31 13:32 【QUICK解説委員長 木村貴】前々回と前回で説明したように、お金は政府によって計画・考案されたものではなく、個人の行動から自然に生まれたものだ。また、長い歴史を経て、人々は優れたお金として貴金属である金と銀を選び取った … 2024/5/24 16:53 【QUICK解説委員長 木村貴】国債は株式などと同様に市場で売買されており、価格は変動するため、券面に記された利率が同じでも、購入した時の価格によって満期までに得られる利回りは違ってくる。満期までに受け取る利息が同じなら … 為替・金利 2024/5/23 14:01 【QUICK解説委員長 木村貴】お金は前回説明したように、商品から生まれる。だからお金として使う以外に、商品として使うことができる。まもなく新札が登場する日本円をはじめ、現代のお金はお金以外に使い道がない。これはお金本来 … 2024/5/17 13:52 【QUICK解説委員長 木村貴】日銀の政策変更や急激な円安など、「お金」にまつわるニュースが相次いでいる。そもそもお金とは何か、その基本のキについてあらためて考えてみよう。 あなたが絶海の孤島に流れ着いたとしよう。あたり … 2024/5/10 14:46 【NQNロンドン=蔭山道子】欧州株式市場で自動車株の上値が重い。電気自動車(EV)を中心とした需要減や中国での競争激化などで2024年1~3月期は各社、販売が苦戦した。新車種の投入などをきっかけとした先行きの収益回復に期 … NQNセレクト 2024/5/8 12:45
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。